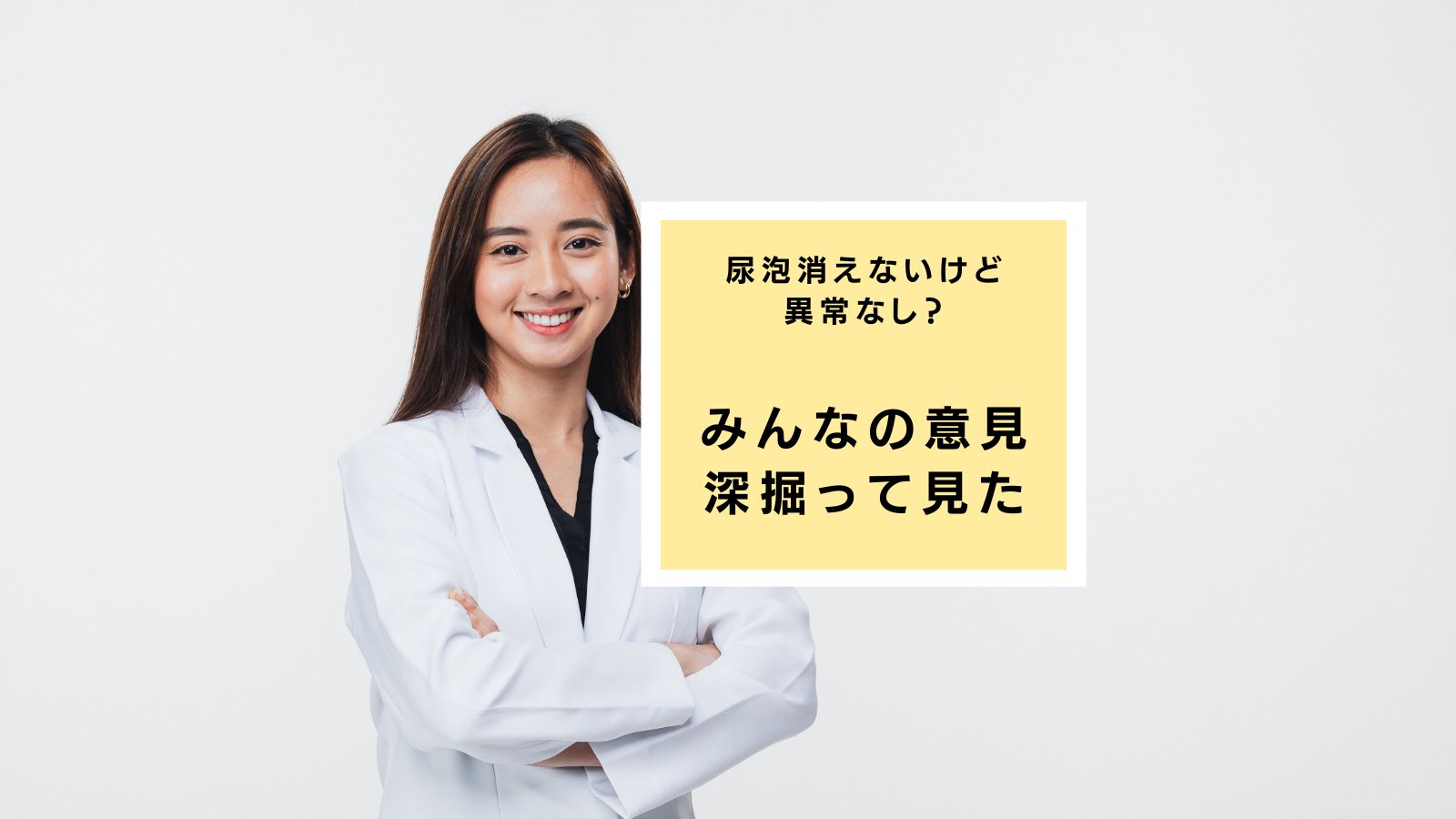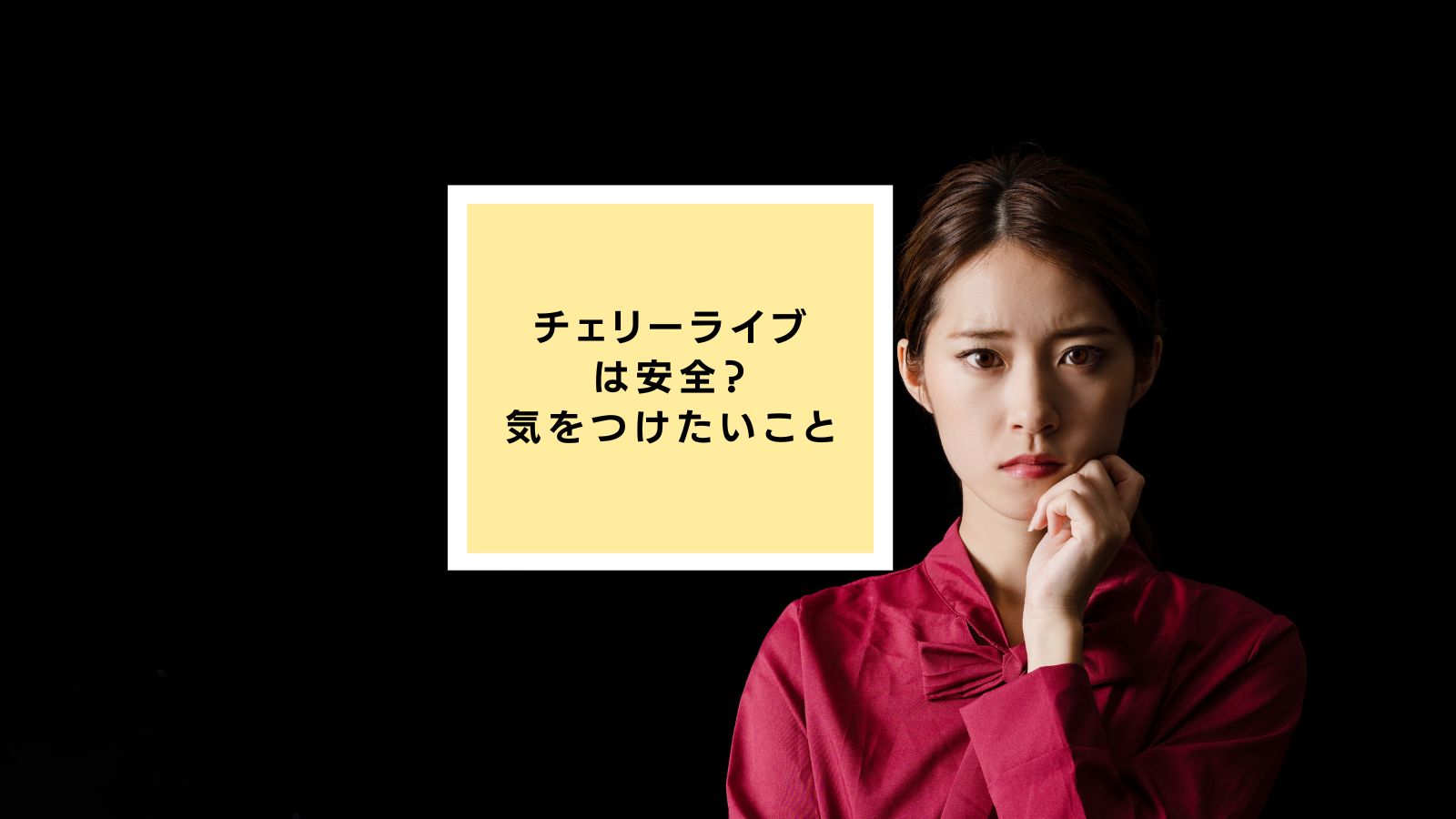おしりから血(鮮血)が出る場合で痛みがない状況は、多くの場合内痔核(いぼ痔)が原因です。内痔核は肛門内部の血管が拡大して形成され、排便時の圧力で血が出ることがありますが、痛みを感じる神経が少ないため痛みは伴いません。
出血は通常鮮やかな赤色をしており、排便時に便器に血が滴ることがあります。しかし、出血が直腸で一時的に留まり、時間が経過すると赤黒い血に変わることもあります。このような症状が見られる場合は、自己診断せずに医療機関での適切な診断と治療を受けることが重要です。
おしりから血(鮮血)痛くないに関する知恵袋の意見
質問の内容
痛くもなんともないのにお尻から血がでました。トイレに入ってお尻がぬれているようだったので拭いてみた痛くもなんともないのにお尻から血がでました。
Yahoo知恵袋
トイレに入ってお尻がぬれているようだったので拭いてみたら血がついていたので心配です。最近急に結構長い距離を自転車で移動するようになったのが原因ですか?
距離は往復10kmくらいです。病院にも気軽にいけないし悩んでいます。どうかアドバイスお願いします。
ベストアンサー
痛くなくても痔ってことありますよ。怖いのはずるずる病院行かないで放置することの方が怖いです。
Yahoo知恵袋
悪化すると手術が必要になります。
痔で入院って周りに知られるほうがいやじゃないですか?早めの受診がいいですよ。
人間たって二足歩行始めたときから痔とはきっても切れない縁になってしまいました。
妊婦なんてほぼほとんどの人が経験者です。私も先生から山ほど軟膏いただきましたよ。恥ずかしがらず早めの治療が大切です。痔じゃなかったらもっとやばいですよ・・。
おしりから血(鮮血)が出る原因
痛みがある時
痛みを伴うおしりからの出血は、多くの場合、裂孔(切れ痔)や血栓性外痔核(肛門の外側にできるいぼ痔)が原因です。これらの状態では、肛門の上皮が裂けたり、血管が炎症を起こしたりするため、排便時に鋭い痛みを感じることがあります。
出血量は通常少なく、トイレットペーパーに血が付く程度ですが、痛みの度合いは個人差があります。痔瘻(あな痔)の場合は、感染により膿と血が混じり合い、痛みを伴うことがあります。
痛みがない時
痛みを伴わないおしりからの出血の主な原因は、内痔核(いぼ痔)です。内痔核は、肛門内部の血管が拡大し、排便時の圧力で血が出る状態です。この部分には痛みを感じる神経が少ないため、出血しても痛みは感じにくいです。
出血は通常、鮮やかな赤色をしており、排便時に便器に血が滴ることがあります。しかし、出血が直腸で一時的に留まり、時間が経過すると赤黒い血に変わることもあります。
おしりから血(鮮血)が出た時に考えられる病気
おしりから血(鮮血)が出る場合に考えられる病気について解説します。この症状は多くの原因によって引き起こされる可能性があり、その中には比較的軽微なものから、より深刻な健康問題まで含まれます。
内痔核(いぼ痔)
内痔核は、肛門内部の血管が拡大して形成される痔の一種です。これは痛みを伴わない出血の最も一般的な原因で、特に排便時に鮮やかな赤色の血が見られます。内痔核は、痛みを感じる神経が少ないため、出血しても痛みは感じにくいのが特徴です。
裂孔(切れ痔)
裂孔は、肛門の粘膜や皮膚が裂けることによって生じます。これは排便時に鋭い痛みを伴い、通常は少量の出血が見られます。裂孔は、硬い便や慢性的な便秘によって引き起こされることが多いです。
血栓性外痔核
肛門の外側にできる痔で、血栓が形成されることが特徴です。痛みを伴うことが多く、しこりのような感触がある場合もあります。出血は内痔核ほど多くはないですが、痛みが強いことが特徴です。
大腸ポリープや大腸がん
大腸のポリープやがんも、おしりからの出血の原因となり得ます。これらの状態では、出血は通常、便に混じって現れることが多いです。特に、大腸がんの場合は早期発見が重要で、定期的なスクリーニングが推奨されます。
炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患も、おしりからの出血を引き起こすことがあります。これらの病気は、腸の慢性的な炎症を特徴とし、出血の他にも下痢、腹痛、体重減少などの症状が見られることがあります。
感染性腸炎
細菌やウイルスによる感染が原因で起こる腸炎も、出血の原因となることがあります。これには食中毒や特定の感染症が含まれ、下痢や腹痛、発熱など他の症状を伴うことが一般的です。
おしりから血(鮮血)が出た時の注意点
おしりからの出血を経験した場合、まずは冷静に状況を観察し、出血の量や色、痛みの有無を確認することが重要です。特に、出血が繰り返し発生する、または大量の場合、大腸がんや大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎などの深刻な病気の可能性も考慮に入れる必要があります。
これらの症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが勧められます。自己判断での治療は避け、専門医の診察を受けることが、症状の正確な原因を突き止め、適切な治療を受けるための最善の方法です。