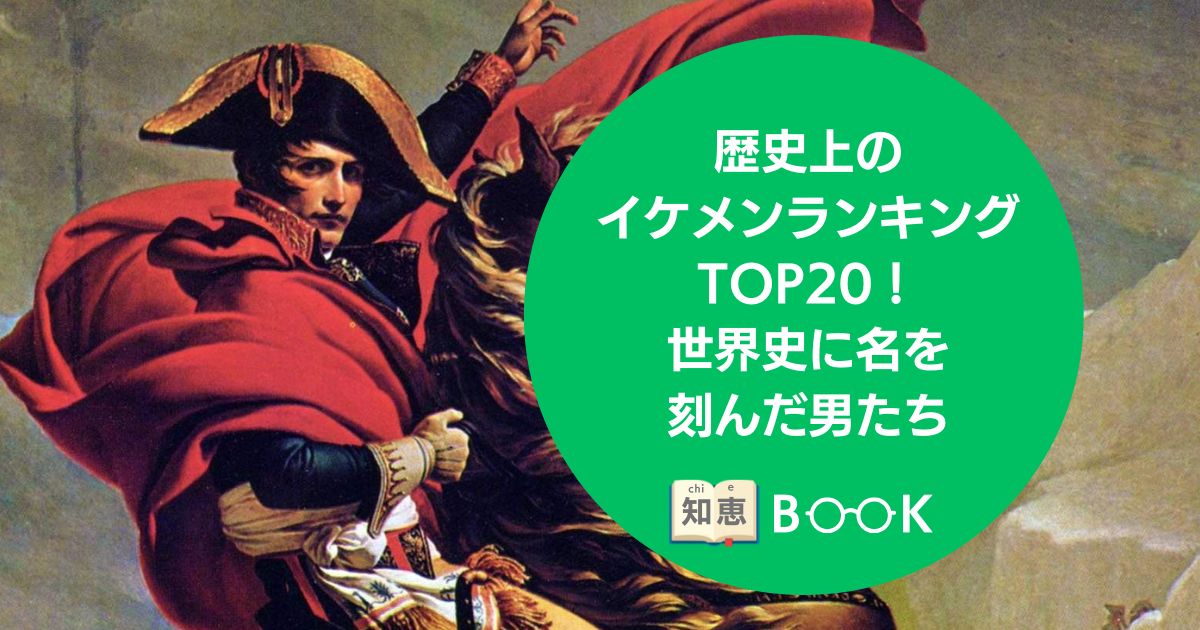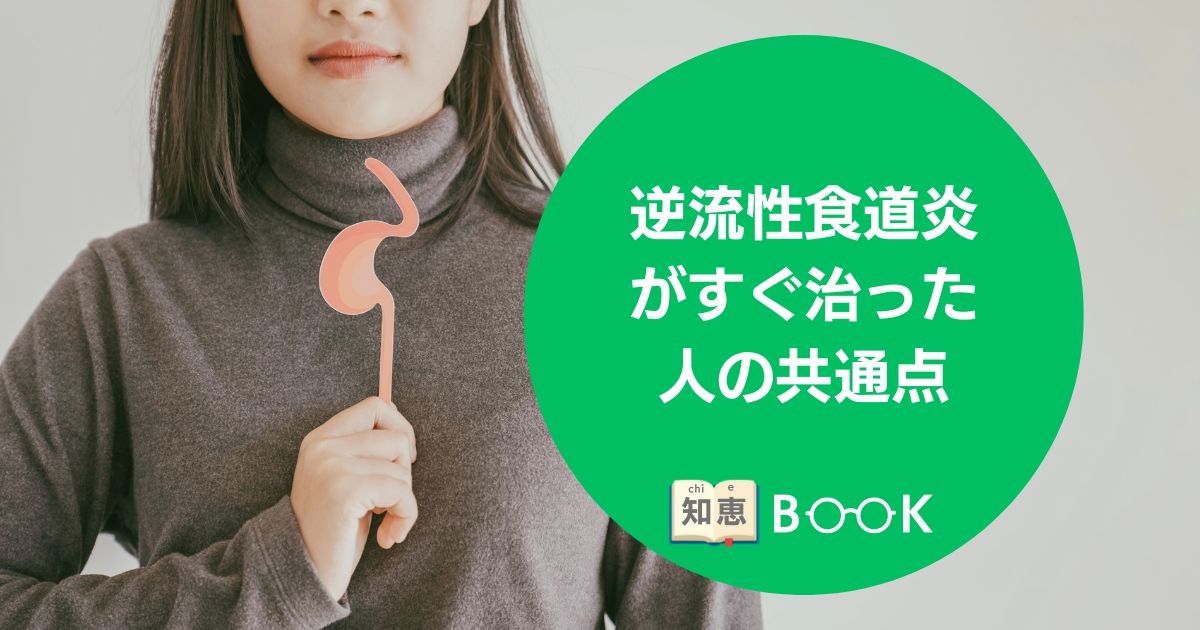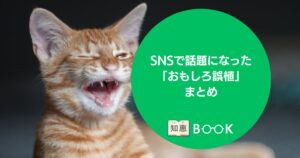剣と知恵で国を治め、時に愛と悲劇を背負いながら、激動の時代を生き抜いた歴史上の人物たち。その中には、容姿の美しさでも人々を魅了した者が数多く存在しました。
本記事では、世界各地の歴史を代表する「イケメン」たちをランキング形式でご紹介します。
古代エジプトの王から中世ヨーロッパの騎士、さらには東洋の文武両道の英雄まで!その風貌は、時代や文化を超えて今なお多くの人々の心を惹きつけています。
彼らの美しさは単なる外見にとどまらず、生き方や人間性にまで及んでいました。「容姿、品格、知性、勇気」本当の“かっこよさ”とは何かを、歴史の中に見出してみましょう。
世界史に登場するイケメン歴史人物ランキング【ベスト20】
第20位:カール大帝(フランク王国)
-e1761139647262.png)
中世ヨーロッパの統一を果たしたカール大帝(シャルルマーニュ)は、壮健な体躯と堂々たる風貌で知られています。身長は2メートル近くあったとされ、筋骨たくましく威厳ある姿はまさに「帝王の中の帝王」。その容貌は数多くの芸術作品にも理想化され、まさに男性の象徴とされました。
第19位:イヴァン雷帝(ロシア)
.png)
恐怖政治で名を馳せたイヴァン4世ことイヴァン雷帝ですが、若年期は非常に整った顔立ちで知られていました。鋭い目つきと端正な顔立ちは、ロシア正教会の中でも「神に愛された容姿」と称された記録が残っています。その美貌と狂気のギャップが、歴史上でも稀有な存在感を放っています。
第18位:スレイマン1世(オスマン帝国)
「壮麗王」の異名を持つスレイマン1世は、政治・軍事・文化の各面で偉大な功績を残しただけでなく、その整った顔立ちと優雅な身のこなしでも人々を魅了しました。トルコ系民族特有の彫りの深い顔と大きな瞳は、多くの詩や物語の題材にもなっています。
第17位:サン・ルイ(フランス王ルイ9世)
フランス王ルイ9世は、敬虔な信仰と高潔な人格で知られる人物ですが、同時にその美しい容貌も多くの史料に記録されています。青い目と金髪というフランス王家特有の気品に満ちた容貌は、民衆から「聖人王」として崇拝されるにふさわしいものでした。
第16位:カエサル(古代ローマ)
古代ローマの英雄ユリウス・カエサルは、その政治手腕と軍事的天才のみならず、女性たちから非常に人気の高い人物でもありました。クレオパトラをはじめとする女性たちとの関係も有名で、彼の整った顔立ちと自信に満ちた物腰は、まさに「男の魅力」の体現とされていました。
第15位:ピョートル大帝(ロシア帝国)
ロシア帝国を近代国家へと変革したピョートル大帝は、身長が非常に高く、堂々とした姿で知られています。 若き時代の肖像画には、切れ長の目と自信に満ちた表情が描かれ、その端正な風貌が「イケメン」の評価となっています。
ただし、改革を断行する厳格さも併せ持っており、そのギャップもまた魅力のひとつと言えるでしょう。
(補足:肖像画は画家の理想像を含むため、実際の容姿とは異なる可能性があります。)
第14位:ホレーショ・ネルソン(イギリス海軍)
イギリスの英雄として名高いネルソンは、軍服姿の肖像画において、整った顔立ちと強い意志が表情から読み取れます。 戦場での活躍だけでなく、若いうちから注目を集めていた風貌も「イケメン」としての評価を支えています。
海軍将校としての威厳とその容姿の両立が、「知的で頼れる男」のイメージを際立たせています。
第13位:ラムセス2世(古代エジプト)
古代エジプトの王ラムセス2世は、多くの巨大モニュメントにその姿が刻まれています。 若々しく堂々とした顔立ちは、古代から「王としてふさわしい顔」として理想視されていたことが伺えます。
その姿は美形としても称賛され、王としての威厳とともに「美しい顔立ち」の歴史的人物として位置付けられています。
第12位:リチャード1世(イングランド王)
「獅子心王」として知られるリチャード1世は、騎士としても王としても名を馳せました。彼の肖像や彫像からは、長い髪と端正な顔立ちが印象的に描かれています。
戦場での剛毅さと王家の気品を兼ね備えたその姿が、人々の「王として美しい男性像」の記憶を形づくったといえます。
第11位:アショーカ王(インド)
古代インド帝国の皇帝アショーカ王は、仏教の庇護者として知られると同時に、その肖像からは穏やかで整った風貌が読み取れます。
美醜だけでなく、慈悲と知恵を備えた王としての人格が「美しい人物」としての評価を高めており、時代を超えて尊敬される存在です。
第10位:徳川慶喜(日本)

幕末から明治維新へと移る激動の時代に、最後の将軍としてその責任を担った徳川慶喜。彼の姿は、落ち着いた気品と覚悟を感じさせ、時代の象徴として多くの人々の印象に残っています。
特にその端正な顔立ちと、時代の波を受け止める毅然とした表情は「イケメン歴史人物」という観点からも評価される一端です。
第9位:ロレンツォ・デ・メディチ(イタリア)

フィレンツェを彩った芸術と文化の寵児、ロレンツォ・デ・メディチ。麗しい顔立ちと洗練された身なり、そして知的な雰囲気が相まって、「ルネッサンス期の美男子」の典型として語られます。芸術家たちに囲まれた彼の姿からは、ただの権力者ではない“魅力あるリーダー”の佇まいが感じられます。
第8位:ナポレオン・ボナパルト(フランス)

ヨーロッパ史上屈指の英雄でありながら、その風貌もまた人々の記憶に刻まれています。ナポレオン・ボナパルトは、力強くも端整な顔立ちと、軍服に身を包んだ姿が有名。画家たちがその姿を理想化して伝えてきたため「帝王らしいカリスマ性あふれるルックス」という印象があります。
第7位:韓信(中国・漢代)
中国・漢の名将として伝説に名を残す韓信。兵法に長け、人心を掴む人柄でもあったとされ、彼の肖像・伝承においては、鋭い目つきと引き締まった顔立ちが描かれてきました。勇猛な将のイメージと整った風貌が「イケメン英雄」としての位置づけを支えています。
第6位:ヘンリー8世(イングランド王)若年期
イングランド王国の歴史を劇的に紡いだヘンリー8世。彼の若年期に描かれた肖像画には、均整のとれた顔立ち、大柄でありながらも王としての威厳を兼ね備えた雰囲気が漂います。「王の中の王」としての風格が、容姿の評価にも繋がったと言えるでしょう。
第5位:チンギス・カン(モンゴル帝国 若年期)
モンゴル帝国を築いたチンギス・カン。若い頃には、草原の荒々しさと同時に、凛とした強さと若々しい魅力を持っていたと伝わります。
征服者としての鋭さだけでなく、部族を纏め上げる統率力・カリスマ性を顔立ちからも想像させ、「世界史を動かした美男子」としての視点でも注目されます。
第4位:サラディン(アイユーブ朝)
イスラム世界を代表する英雄サラディン。
信義と強さを兼ね備えた指導者として知られ、数多の後世の画家・歴史家によってその姿が描かれてきました。彼の描写には、深い眼差しと整った顔立ち、そして王としての品格が感じられます。
第3位:トトメス3世(古代エジプト)
古代エジプトの偉大な王トトメス3世。その姿は壁画や彫像によって多く残されており、若々しく引き締まった顔立ちと王の威厳を兼ね備えた造形が印象的です。古代から「王は美しいものであれ」という価値観のもと、彼の容姿は王に相応しいものとして理想化されてきました。
第2位:アレクサンドロス大王(マケドニア)
アレクサンドロス大王は、若くして広大な帝国を築いた英雄で、その肖像からは「理想の王」の風格が感じられます。巻き毛の髪、遠くを見つめる瞳、そして均整のとれた顔立ち…これらが“王の容姿”として後世にまで大きな影響を与えています。
第1位:マクシミリアン1世(ハプスブルク家)
栄えある第1位にはハプスブルク家のマクシミリアン1世を据えました。彼は政治的にも文化的にもハプスブルク家を隆盛に導いた皇帝であり、その顔立ちは数多くの肖像画で“理想の貴族男性”として描かれています。
均整のとれたプロポーション、落ち着いた表情、知性を伴う静かな威厳…。このすべてが「歴史上の究極のイケメン」としての評価を支えています。
世界各国の文化に見る「イケメン像」の違い
古代ギリシャ・ローマにおける理想の男性像
古代ギリシャおよびローマにおいて、理想的な男性像は「均整のとれた身体」「整った顔立ち」「知性と徳を備えた人格」が三位一体となった存在でした。彫刻に見るアポロン像やアスリートの裸体像には、若々しく引き締まった肉体美が強調され、肉体的な美しさが徳と結びついていました。
ローマ時代には、政治家や軍人の彫像にも理知的な表情が加わり、外見と内面の両面における「完成された男」が理想とされました。
中世ヨーロッパの騎士と王族の美的価値観
中世ヨーロッパでは、戦場での勇敢さに加え、礼儀作法や信仰心、女性への献身といった「騎士道精神」が重視されました。そのため、イケメンとは単に容姿の良さだけでなく、態度やふるまいを含む「品格ある紳士」であることが求められました。
貴族や王族の肖像画では、細面で鼻筋の通った顔立ちや、長い金髪、白い肌などが理想像とされており、それらが「高貴な血筋の証」とも見なされました。
東洋(中国・ペルシャ・インド)における容姿の評価基準
東洋においても、イケメンの定義は地域と時代によって異なります。古代中国では、眉目秀麗、すなわち「きりりとした眉と澄んだ目」が美男子の条件とされ、王族や文人の間では細身で端整な容姿が好まれました。
ペルシャでは、濃い眉や大きな瞳といった彫りの深い顔立ちが理想とされ、インドでは宗教的・精神的な清浄さとともに、優雅な身のこなしや微笑みが尊ばれました。いずれも容姿と人間性が一体となった「品ある美しさ」が評価基準でした。
現代人の視点で再評価される歴史的人物の魅力
現代においては、写真技術や肖像画の再分析、さらにはCG復元などを通じて、過去の人物の姿をより現実的に捉えることが可能となりました。その結果、当時「普通」とされた顔立ちが現代的感覚では非常に整って見えたり、逆に理想化された肖像画が現実とはかけ離れていたりする事例も見られます。
また、現代では「外見」だけでなく「生き様」や「内面の強さ・優しさ」までも含めて「イケメン」と捉える傾向が強くなっており、歴史上の人物の評価も多面的に再構築されつつあります。